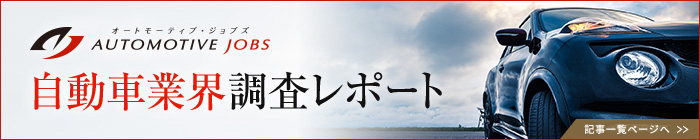【日系メーカー】主要完成車メーカー エンジンバルブ制御技術採用レポート
2018.03.01
トヨタ
▽アトキンソンサイクルエンジンとVVTシステム
トヨタは、エンジンの燃焼効率を引き上げるため、アトキンソンサイクルと呼ばれる圧縮工程を展開。
―エンジンの出力を抑える場合、エンジンへの吸気量をスロットルバルブで縛らず、開けたまま吸気させ、ポンピングロスを低減させる技術。Priusなどハイブリッド車を中心に展開中。
2016年12月、トヨタがTNGA用新型2.5ℓ直列4気筒(直4)直噴ガソリンエンジン(GE)のDynamic Force Engineを公開。
―同エンジンは、TNGAの設計思想に基づき、エンジンの基本構造や構成を見直して、環境性能と走行性能を両立させる「Dynamic Force Engine」のコンセプトの下、開発を推進。
―出力と燃費の両立を目指し、従来のポンピングロスや排気、冷却、フリクションによる各損失の低減に加えて、高速燃焼の追求と吸入効率化を実現し、その燃焼方式を他のエンジンにも展開する。
―吸排気系(主にバルブ)では、バルブ狭角を従来の31°から41°に拡大したほか、ボアストローク比を1.2として、従来の90×98(mm)から87.5×103.4(mm)に変更。 適切な燃焼のための吸排気機構を実現。
 ▽2.0ℓ 8AR-FTSエンジンとDual VVT-iW
▽2.0ℓ 8AR-FTSエンジンとDual VVT-iW
8AR-FTSエンジンでは、エンジン回転の全領域において高トルクを確保するため、吸排気バルブの開閉タイミングを走行状況に合わせて最適に制御するDual VVT-iW(Dual Variable Valve Timing-intelligent Wide)機構を採用。
―吸気バルブを閉じるタイミングを従来エンジンに比べて遅らせて圧縮行程のポンピングロスを低減。これにより、高効率のアトキンソンサイクルの実現と燃費の改善につなげた。
ホンダ
▽VTEC(可変バルブタイミング・リフト機構)技術
ホンダは、燃費と動力性能を両立する1.0ℓ直3ガソリンエンジンの技術詳細を発表。
―マルチホールインジェクターをサイドにマウントした高タンブル吸気ポートにより、急速燃焼を実現。

 ―デュアルVTC(可変バルブタイミングリフト)とVTEC(可変バルブタイミング・リフト電子制御システム)を吸気バルブに用いることで、アトキンソンサイクルを実現するための低バルブリフトモードを可能にした。
―デュアルVTC(可変バルブタイミングリフト)とVTEC(可変バルブタイミング・リフト電子制御システム)を吸気バルブに用いることで、アトキンソンサイクルを実現するための低バルブリフトモードを可能にした。
―さらに、最新の低フリクション技術なども組み合わせた結果、先代エンジン比で26%の燃費改善を実現した。
―2017年8月に660ccエンジンにもVTEC技術を適用。
日産
▽eVTC技術 電磁式CVTC(=Continuous Valve Timing Control)。
電磁クラッチとヘリカルギアを利用した連続可変バルブタイミング機構で、electronic Valve Timing Controlの略称。可変バルブ機構にモーターではなく電磁石を利用した。
―eVTCユニットについて、日鍛バルブと共同で開発。
―eVTCは、VQ35DE(V6 3.5ℓガソリン)エンジンなどで採用。
2016年5月、Schaefflerと共同で電動式可変バルブタイミング機構のECP(Electric Cam Phaser)を開発したと発表。
―ECPでは、Schaeffler開発の減速機構のウェーブジェネレーター(波動歯車機構)を採用し、構造を単純化することでモーターを含んだアクチュエーターを小型化するとともに、減速比と高機械効率を実現。 ―ECPでは、電気モーター(アクチューエーター)とギアボックスによりバルブの開閉タイミングを制御。エンジンの油圧に依存しないため、エンジンの始動直後から可変バルブ機能を使用可能であり、より精密な制御が可能。このほか可変速度の向上による高い応答性を実現する。
▽ミラーサイクル技術を導入
2012年よりNoteに搭載されたHR12DDR(1.2ℓ)ガソリンエンジンでは、吸排気損失(ポンピングロス)を低減するため、吸気バルブを通常エンジンより長く開く、ミラーサイクル(Miller Cycle)を採用。
―圧縮行程では、吸気バルブが閉鎖するが、ミラーサイクルでは吸気バルブが開いたままで、空気の吸入量増加による燃焼効率の向上を図った。

マツダ
▽SKYACTIV-GのVVTシステム
マツダの新世代ガソリンエンジンSKYACTIV-Gにおいて、吸気側に電動制御のバルブタイミングS-VTを導入。
―SKYACTIVでは燃焼効率化に向け、高精度なバルブ制御を導入。
―バルブの吸気遅閉じによるポンピグロスを減らすほか、燃焼時でのバルブ吸気閉じを素早く正確に行う必要があるため、吸気側のバルブ開閉システムに精密な制御が可能である電動式を用いた。
―高精度バルブタイミングと高圧縮比化により燃費と出力を両立。
―マツダはSKYACTIV-Gを2011年のDemio(海外名Mazda2)へ投入したのを皮切りに、主力モデルへの搭載を進めている。
▽SKYACTIV-DのVVLシステム
マツダのSKYACTIV-Dにおいて、吸気側バルブにVVL(可変バルブリフト機構)を採用。始動後の暖気運転中に発生する半失火状態を抑制。
また、吸入行程中にわずかにバルブを開き、排気ポート内の高温の残留ガスをシリンダー内に逆流させ、空気温度を高め、圧縮時の温度上昇を促進し、着火安定性を図った。
 <FOURIN世界自動車技術調査月報(FOURIN社 転載許諾済み)>
<FOURIN世界自動車技術調査月報(FOURIN社 転載許諾済み)>